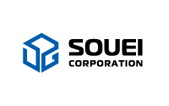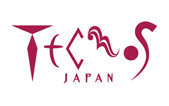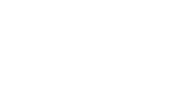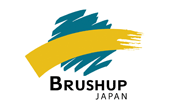このたび取材をさせていただいたのは、『ベイビー・アイラブユー』(TEE)や『Hero』(安室奈美恵)をはじめ、おそらく誰もが耳にしたことのあるメガヒット曲を生み出した音楽家、今井了介氏である。直近では、東京2020オリンピック・パラリンピックにおける「チーム コカ・コーラ」公式ソング『Colorful』の総合プロデューサーも務め、長引くコロナ禍で塞ぎかけていた私たちの心に、再び希望の灯をともしてくれた。大会理念にも通ずる“ダイバーシティ(多様性)”をテーマとした同楽曲は、世界中から豪華14組のアーティストが集結。人種、国籍、性別、年齢、キャリアなどを超えた、まさに“カラフル”な世界観を体現し話題となった。今井氏は、25年を超えるキャリアのなかで、強い信念と行動力をもって日本の音楽シーンを変革させてきた、まさにその人である。それはつまり、誰もやらなかったこと―――。たとえば、今や日本の音楽シーンにおいて当たり前に浸透しているR&Bのスタイルがあるが、それは約20年前、彼が生み出した一つの楽曲が契機となっている。また、2005年に法人化した『TinyVoice, Production』における若手作家やプロデューサーの育成を通じて、日本のポップミュージック・シーンの発展に貢献してきた。その実績は、チーム全体でCD7,000万枚以上、配信では1億ダウンロード以上のセールスを記録している。そんな今井氏が新たに起業し、2019年にローンチしたのが、飲食ギフトサービス『ごちめし』である。一見すると、彼のキャリアとはかけ離れた事業であり、まるで脈絡がないかのようにさえ感じる。しかし、それは確実に彼自身の人生や価値観と繋がっており、音楽家である今井氏ならではの、既存のサービスにはない発想とビジョンが散りばめられていた。今回は、彼の幼少期へ遡るところから、この事業の本質を紐解いていく。
 気持ちを“ごちそう”にして贈れるWebサービス・アプリ『ごちめし』。
気持ちを“ごちそう”にして贈れるWebサービス・アプリ『ごちめし』。
『ごちめし』は、離れた場所にいる相手にも、気軽にスマートに、お食事をごちそうできる(=ごちれる)サービスです。使用シーンの例としては、誕生日や記念日を迎える友人への「お祝いごち」、お世話になった人への「お礼ごち」、大好きなお店を誰かに知ってもらうための「応援ごち」など、さまざまな使い方があります。特徴は、いつでも、どこからでも、登録店舗のメニューから好きな料理を指定して、ごちそうしたい相手にメールやSNSなどでプレゼントできること。URLを受け取った人は、お店に行ってそのページを見せるだけで、料理を楽しめるという仕組みです。
このサービスには、実は“元ネタ”があります。出逢いは偶然、SNSのタイムラインで、北海道・帯広にある『結(ゆい)』という食堂を見つけたのが始まりでした。SNS上で話題となっていたのが、店主の本間さんが考案された、『ゴチメシ』という仕組み。なんと、彼のお店で食事をしたお客様の多くが、地域の中高生のために食事代を余計に支払って帰るというのです。大人たちが善意で寄付した食事代(ゴチメシ)のおかげで、お腹をすかせた若者が、無料で食事ができるわけです。こんな素晴らしい循環をカタチにした店主・本間さんの動機がまた素敵なのです。東京での会社員生活を終え、数十年ぶりに地元に戻った彼は、若者たちの味覚が、時代の変化によって画一化していることを気がかりに思いました。帯広は、ジャガイモ一つとっても、品種によって味わいの違いが感じられるような食の豊かな地域です。しかし、昨今ではファストフードやコンビニが台頭し、地元の味が影を潜めていました。せっかくの地元の美味しさを、若者たちに伝えたい…。そんな想い一つで、十勝の恵みを活かした“カレー”や“うどん”が味わえる食堂をオープン。若者に足を運んでもらうための試行錯誤の結果、ようやく実を結んだのが『ゴチメシ』のアイデアだったのです。僕のなかに、電撃が走りました。この仕組みは、「ごち」される人の喜びはもちろん、「ごち」する人にも確実に喜びが生まれるはず!そして、『結』という空間が、このような素敵な喜びの連鎖を生み出し続ける場になっている。もしもこの仕組みを、デジタルで全国に拡散できたら、絶対に面白いことになる…!僕らは本間さんに逢うために、帯広へ飛びました。そして、『ゴチメシ』の聖地にて「ごち」の儀礼を終えたあと、本間さんに『ゴチメシ』のアプリサービス化を提案させていただいたのです。『ゴチメシ』というネーミングも、これ以上に素晴らしいものはありません。何度か帯広へ通うなかで商標登録もご一緒させていいただくことになり、2018年の末頃に、本格的なアプリ開発がスタートしました。
加盟店舗の利用料ゼロ、新機軸のサービスモデル。
そんなルーツを持つ『ごちめし』が目指すのは、“人にもお店にも、最もやさしいサービス”であること。クーポンやデリバリーをはじめ、飲食に関わる既存サービスのほとんどが、売上から多くの手数料を店側に要求するのが一般的となっています。なかには手数料率が35%に上るものもあり、そうなると飲食店側が利益を泣くか、または手数料分を価格に上乗せし、ユーザー側に負担を強いることになります。そこで我々は、人にもお店にも、もっと寄り添った仕組みをつくりたいと考えたのです。『ごちめし』は、食事を贈る人から10%のみ手数料をいただき、店舗側には利用料・手数料は発生しません。飲食店にとって負担がなく、お店や料理の広告宣伝にもなる新たなサービスモデルとして認知いただき、現在16,000店舗以上(2021年9月時点)のお店に参加いただいております。
コロナ禍を“先払い”で救う飲食店応援プロジェクト『さきめし』で急成長。
 2019年10月末、満を持して『ごちめし』アプリをリリースした直後のことでした。年明け早々、新型コロナウィルスの感染拡大が始まり、国民への外出自粛要請が出されたのです。瞬く間に飲食店の苦境が報じられ、我々も出鼻をくじかれた形となりました。しかし、不幸中の幸いにして、『ごちめし』のプラットフォームは、先行きの見えない飲食店の支援にそのまま活用できることに気づいたのです。本来であれば誰かに食事を贈るためのサービスですが、外出自粛要請下においてはそれも叶いません。そこで、まずはユーザーにお食事代を先払いしていただき、感染拡大が落ち着いた頃にお店に足を運んでいただけるよう、急遽の転換を図りました。2020年3月9日、『さきめし』としてリリースしたところ、「自分の好きなお店を応援したい!」という支援者と、経営の見通しが立たない飲食店をつなぐ活動が、大きな輪となって広がりました。同年5月には、サントリーグループに1億円を拠出いただき、参加店への寄付に加えて、ユーザーの手数料を一定期間無償にしたことで、飲食店応援プロジェクトを大きく飛躍させることができました。サントリーさんのような大企業に、こうした善意の輪が伝わったのは、非常に感慨深いものでした。
2019年10月末、満を持して『ごちめし』アプリをリリースした直後のことでした。年明け早々、新型コロナウィルスの感染拡大が始まり、国民への外出自粛要請が出されたのです。瞬く間に飲食店の苦境が報じられ、我々も出鼻をくじかれた形となりました。しかし、不幸中の幸いにして、『ごちめし』のプラットフォームは、先行きの見えない飲食店の支援にそのまま活用できることに気づいたのです。本来であれば誰かに食事を贈るためのサービスですが、外出自粛要請下においてはそれも叶いません。そこで、まずはユーザーにお食事代を先払いしていただき、感染拡大が落ち着いた頃にお店に足を運んでいただけるよう、急遽の転換を図りました。2020年3月9日、『さきめし』としてリリースしたところ、「自分の好きなお店を応援したい!」という支援者と、経営の見通しが立たない飲食店をつなぐ活動が、大きな輪となって広がりました。同年5月には、サントリーグループに1億円を拠出いただき、参加店への寄付に加えて、ユーザーの手数料を一定期間無償にしたことで、飲食店応援プロジェクトを大きく飛躍させることができました。サントリーさんのような大企業に、こうした善意の輪が伝わったのは、非常に感慨深いものでした。
また、国内最大のクラウドファンディング『CAMPFIRE』、Instagramのギフトカード機能をはじめ、支援・ギフト領域の他サービスとの連携を強化したことで、着々と認知度も向上しています。おかげさまで、一連の「さきめし」プロジェクトは、『2020年度グッドデザイン・ベスト100』(主催:公益財団法人日本デザイン振興会)の受賞をはじめ、数々の賞をいただくことができました。
自分が音楽家になるなんて、夢にも思っていなかった。
生まれは東京、プロの音楽家の両親のもとで育ちました(両親は幼い頃に離婚しており、僕は一人っ子でした)。父はクラシックの楽団に所属するホルン奏者、母はピアノの先生でした。そんな環境だったので、うちで「音楽」といえばクラシックのことを指していました。たとえば、年末に観るテレビ番組といえば『紅白歌合戦』ではなく、『第九』や『ウィーン・フィル』のニューイヤーコンサート。ポップスの流れる音楽番組を観る機会は皆無でした。僕自身、幼い頃に少しだけピアノをやった時期がありますが、母の教えが厳しすぎて、すぐにイヤになってしまいました(笑)。まさか自分が音楽家になるなんて、当時は夢にも思わなかったですね。
「協調性がない」と言われ続けた子ども時代の記憶。
僕には学校の先生から、いつも指摘されてきたことがあります。それは、「協調性がない」ということ。それこそ幼稚園時代から高校を卒業するまで、通知表のコメント欄には必ず書かれていました。別に誰かを攻撃するわけでも、ケンカするわけでもないのですが、いま思えば、単に周囲に馴染めず、浮いた存在に見えたのでしょう。忘れもしない、小学校高学年のときのこと。クラスメートと仲良くするよう先生に注意された僕は、別にケンカをしたわけでもないのに納得がいかず、思わず反論しました。なぜ自分が選んだわけでもない人たちと、たまたま生まれ育った場所や時期でクラスが同じになったというだけで仲良くしなければらないのか…と。すると先生から、「そういうものではないんです!」と頭ごなしに怒られ、ますますモヤモヤするという…(笑)。昔から、何かに無理やり当てはめられることに、いちいち違和感を覚えてしまうタイプだったのです。
僕が通っていた中学校は、お笑い芸人の品川ヒロシ氏(品川庄司)の半自伝的小説『ドロップ』の舞台にもなった、いわゆるヤンキーの多い地域にありました。僕が入ったのは園芸部。その実質は帰宅部のようなもので、10人ほどのメンバーは、僕を除いてみんな不良の幽霊部員。誰ひとり活動しないので、必然的に僕が部長です(笑)。10人分の畑を思いのままに耕し、ひたすら野菜づくりに没頭しました。毎日のように畑に足を運び、かなり真面目に活動していましたが、我ながら相当な変わり者だったと思います…。
高校生になった途端、僕は絵に描いたようにドロップアウトしていきます。通っていたのは、都立の有名進学校。クラスメートの半分以上が、東大や有名私大に合格するような学校でした。中学まではわりと勉強ができた僕も、服装自由、生徒の自主性を重んじる校風が悪いほうに働いてか、急速に勉学から遠のいていきました。真面目に授業さえ受けていれば、幾多の生徒が東大へ行く…。そんな決まりきったコースに、少しも興味が持てなかったのです。
当時はバブルの真っ盛りで、東京の湾岸エリアの開発が盛んに行われていた時代です。『芝浦GOLD』や『インクスティック芝浦ファクトリー』など、大型ディスコが一世を風靡していました。週末になると、東京中の遊び人がウォーターフロントめがけて集結します。僕みたいな高校生がふらりと入れるような場所ではなかったのですが、そのような場所にいる大人たちと知り合いになれば、いつも歓迎してもらえました。最先端の音楽に触れ、片時もウォークマンを手放さなかった僕は、学校に自分の居場所を見出せないでいた空虚感を満たすことができました。大音量で流れる音楽…。サンプリングやトラックメイク、シンセサイザー…そこには今まで経験したことのない、キラキラした興奮があったのです。そんな世界に魅せられてしまった僕にとって、学校での日常は、ますます退屈なものへと変わっていきました。ちなみに一度、シンセサイザーを購入してみようと値段を調べてみたら、その高さにひっくり返りそうになったものです。やはり音楽なんてやるものではない…この頃はまだそう思っていました。さらに、当時は空前のバンド・ブームでもあり、いわゆるイケてる男子はバンド活動をするのが主流でした。しかし、高校の文化祭で、あまりに酷い彼らの演奏を聴いて、余計に人前で音楽をやることに現実味を持てなくなっていました(笑)。幼い頃からクラシックのオーケストラに触れてきた僕の耳は、さすがに肥えていたようです(当時の同級生たちには申し訳ないと思っています…)。
このように、僕は音楽を心から好きではありながら、それを職業にしたいとは思っていませんでした。その本質的な理由は、両親がやっていることに対する稚拙な反抗心がどこかにあったこと。そして、両親が音楽で食べていくことの大変さを身をもって経験しているからこそ、息子には同じ道を歩んでほしくないという親心を、子どもながらに感じとっていたからです。特に母親は、僕が大学へ進学し、終身雇用が約束された安定企業へ就職することを強く望んでいました。僕自身は大学へ進むのではなく、絵描きや映像作家など、なにか創作に携わる仕事に就きたいと考えていましたが、そんな母の意向もあって、大学受験をしてみることにしたのです。しかし、一年浪人して入った大学を、僕は1年も経たずに辞めてしまいます。入学したのは明治大学の理工学部でしたが、なにか将来を見据えて進学先を選んだわけではありません。単に受験科目として、理系科目のほうが得意だっただけ。入学直後のオリエンテーションに参加した時点で、こんな無自覚な環境に4年間も居続けるのは無理だと確信してしまったのです。
大学中退。15万円を握りしめ、ひとり中国放浪の旅へ。
大学を早々に辞めたことで母には呆れられ、さすがに家にも居られなくなった僕は、これから何をやっていけば良いのか、自分でも見失っていました。そこで、この機会に旅に出ようと決意したのです。その動機は、「ここではないどこかへ行きたい」という逃避願望と、「知らない世界を見てみたい」という純粋な好奇心の半々だったと思います。アルバイトをしたり、服を売ったりして手元にあった全財産は15万円ほど。今から30年前、その金額で最も長く行ける外国といえば、まだ圧倒的に物価の安かった中国でした。当時は船で大陸に渡るのが貧乏旅行の定番。もはや貧乏学生ですらない単なる貧乏(時間だけは大富豪!)の僕はバックパックを背負い、横浜のみなとみらいから独りで船に乗り込みました。そこから片道3泊4日ほどかけて上海へ渡るのです。船内では、僕と同じくバックパックで旅をする日本人の若者や、自国へ帰る中国人の学生たちに出逢いました。このときふと、「協調性がない」と言われ続けてきたはずの自分が、彼らと自然に仲良くやれていることに気づいたのです。バックパックに入れたカップラーメンを交換条件に、現地で使える中国語を教わったり、逆に日本語を教えてあげたり…。たとえ偶然に同じ空間を共にすることになった相手でも、それぞれの目的を持つ者同士であれば、(散々協調性がないと言われ続けてきた私でも)こんなにも自然に打ち解けられる…。やりたいことに向かっていく限りにおいては、やっていけるかもしれない…。そんな自信が初めて湧いてきた、印象的な経験でした。
その当時の上海は、現在の姿からは想像できないほど発展途上の段階にあり、街中のいたるところがへドロ臭いし、今や未来的なビルがそびえる浦東新区も、あたり一面、沼と田んぼでした。物価は驚くほどの安さで、1食あたり30円もあれば、屋台で充分にお腹を満たすことができました。格安のドミトリーに泊まり、電車やバス、ヒッチハイクで移動するわけですが、当時の中国は、まさに社会主義の極みのような状態。切符は客が“売っていただくもの”で、こちらが中国語を話せなければ、まったく相手にされません。必死にしがみついて漢字で筆談をせがみ、ようやく伝わったものの、次の列車は翌日の早朝便…なんてこともありました。仕方なく、その日は駅で寝泊まり。現地で買った小さなアコーディオンを弾いて、小銭を稼いだりして過ごしました(笑)。上海からシルクロードを辿るように、西安、そして敦煌へ。砂漠のド真ん中にある敦煌の町は、日本人には想像もつかないほどの凄まじい乾燥地帯です。それはもう、洗ってびしょびしょに濡れたデニムが、数時間のうちにパッキパキに乾くほど…。旅の疲れが出たのか、僕はそこで高熱に倒れました。こんな状態で襲われて砂漠に捨てられたら、僕はここで誰にも見つからないまま朽ち果ててしまうかもしれない…。高熱と恐怖にうなされながら、旅は4日間ほど立往生しました。ようやく回復すると、懲りずに西へ渡り、ウイグル自治区のウルムチ・トルファンから南下してパキスタンの山を越え、インドへ。そして再び中国へ戻り、モンゴルの国境あたりを旅して北京へ。帰国するまで、約2ヵ月間の旅となりました。いま思えば、なんと命知らずな旅をしたのだろうと我ながら思います。若気の至りによって成しえた、人生で二度と経験できない冒険となりました。
夢だった絵の仕事を始めるも、現実の厳しさを知る。
中国放浪の旅を終えると、すぐに現実が待っていました。大学を辞めた時点で、当然ながら母親と自活を約束した僕は、横浜で借りたワンルームで一人暮らしを始めていました。仕事をしなくてはなりません。まずはずっと憧れていた、絵やグラフィックの仕事から始めてみました。しかし、どうしたって食べていける気配がないのです。そもそも仕事が少ないうえに、せっかくいただいた案件でさえ、自分のこだわりが強すぎて、チャンスを潰してばかりいたのです。たとえば、自分の渾身の一作に対して、クライアントから修正依頼がくると途端にイヤになってしまうのです。「そこを変えてしまったら、もはや僕の作品ではない!」なんて言って…(笑)。仕事というのは当然、クライアントの意向あってのものです。しかし、当時19歳だった僕は、自分の愚かさに気づくことができませんでした。キャリアも実力もないくせに、主張ばかりが強くて、ビジネスとしての視点が完全に欠落していたのです。そんな調子ですから、ますます孤立していきます。絵がダメなら写真はどうかとやってみましたが、結局すぐに行き詰まりました。気づいたときにはもう、食うや食わずの生活に…。貧乏すぎて、具なしの自炊カレーピラフなどで食いつなぎ、ついには家賃も滞納する事態まで追い詰められていきました。
人生で初めて、「音楽」を仕事にしようと決意する。
 ちょうど20歳になったばかりの頃です。僕が絵や写真の職業を諦めるのと同時に、知り合いの先輩が、音楽の道に見切りをつけるタイミングが重なりました。楽器や機材が不要になるので欲しいかと聞かれ、僕は即答で譲ってもらいました。このときが、音楽をやってみようと心に決めた瞬間でした。特になにか、自信や考えがあったわけではありません。ただ、音楽は幼い頃からずっと身近にあったものだし、それまでは自分で作ったり、演奏したりということがイメージできなかっただけ。でも、なぜかこのタイミングで、僕には高くて買えないと思っていた機材が、魔法のように目の前に転がり込んできたわけです。僕は音楽をやっていくんだ…。遠回りしたけど、やっぱり音楽だったのかも…と、人生で初めて確信めいたものを感じました。
ちょうど20歳になったばかりの頃です。僕が絵や写真の職業を諦めるのと同時に、知り合いの先輩が、音楽の道に見切りをつけるタイミングが重なりました。楽器や機材が不要になるので欲しいかと聞かれ、僕は即答で譲ってもらいました。このときが、音楽をやってみようと心に決めた瞬間でした。特になにか、自信や考えがあったわけではありません。ただ、音楽は幼い頃からずっと身近にあったものだし、それまでは自分で作ったり、演奏したりということがイメージできなかっただけ。でも、なぜかこのタイミングで、僕には高くて買えないと思っていた機材が、魔法のように目の前に転がり込んできたわけです。僕は音楽をやっていくんだ…。遠回りしたけど、やっぱり音楽だったのかも…と、人生で初めて確信めいたものを感じました。
これは実際に始めてみてわかったことですが、絵や写真よりも、音楽を仕事にするほうが、なんとなく趣味が実益に繋がりそうな予感がありました。その理由は、僕にとって音楽を生業とすることは、良い意味で“2番目”にやりたいことだったからです。一方で絵は、僕が何より好きで、望んでいた職業でした。だからこそ、ひとり夢見て突っ走ってしまい、冷静さや客観性に欠けていたのです。その点、音楽については、作り手としてのこだわりがガチガチに固まっていなかったぶん、商業ベースのなかで自分に何ができるのかを、客観的に考えられる余地がありました。このように、絵をやっていたときに比べて格段に柔軟になれた一方で、僕には自分の作りたい音楽が明確にありました。それは、海外のR&Bのクオリティと遜色のないトラックに、日本語を乗せた形の音楽…すなわち本物のR&Bを、メインのポップスとして日本の音楽シーンに浸透させていくことでした。その当時、日本のポップスシーンで流行っていたいわゆるR&Bは、海外のオントレンドの楽曲と比べて明らかなギャップがあり、僕は大いに違和感を抱いていたのです。世間では当時、小室哲哉サウンドと呼ばれる音楽やモー娘。などが全盛期で、僕はそれを横目で見ながら、自分のやりたい音楽との違いを感じ取り、だからこそ世に出ていけるチャンスがあるのではないかと考えていました。大げさにいえば、時代をひっくり返せるかもしれない…そんなふうに思っていたのです。
幼少期の環境が恵んでくれたもの。
父が所属していたオーケストラのコンサートに、幼い頃から触れてきた自分は、いま思えば実に恵まれた環境にいました。父が演奏するホルンという楽器は、トランペットやヴァイオリンなどリードになり易い楽器に比べて、わりと地味な部類に属する楽器で、子どもの耳にはよく聞き取れませんでした(もちろん温かみのある素敵な楽器です)。僕は父の演奏を聞き取りたい一心で、ホルンの音色を夢中で聴き分けるようになったのです。気づいたときには、100名規模のアンサンブルを構成する楽器の音が聴き分けられるようになり、あたかも音楽を解剖するかのようなイメージで聴くことが癖になっていました。その過程で養われた絶対音感をはじめ、幼少期に培った経験の数々が、音楽家としての僕の現在に繋がっていることは言うまでもありません。
ステージに立つのではなく、音楽の作り手を選んだ理由。
僕は性格的に、人前に出ることが決して好きではないタイプの人間です。だから音楽を生業にするにしても、自分がステージに立ちたいとか、または有名になりたいとか、その種の願望は一切ありませんでした。単純に、歌やダンスの才能がなかったこともありますが(笑)。あくまで音の作り手であること。そこには興味を持てたし、音楽の構造が手にとるようにわかる自分にならできる気がしたのです。たとえばアーティストの場合、見た目やスター性、そして声質など、持って生まれた類の才能がどうしても求められる宿命にあります。しかし、僕が目指していた音の作り手という立場は、それらとは関係のない部分――つまり、自分の努力や情熱によるところ、要は「いい曲が書ける」という一点において勝負できる可能性があったので、賭けてみる価値を感じたのです。そして、音楽の仕事に長く従事し、それを好きであり続けるためには、優秀な“裏方”としてのポジションを確立していくことが何よりの勝ち筋に見えました。
ちなみに僕が裏方的な存在に惹かれ始めたきっかけは、幼い頃の経験にあります。たとえば、オーケストラのコンサートを父の隣で聴いているとき、「この一糸乱れることのない音のすべてをコントロールしているのは、中央で背を向けて、タクトを振っている“あの人”に違いない」…と、いつも興味を惹かれたものです。また、マイケル・ジャクソンのレコードに夢中になったときも、「この“クインシー・ジョーンズ”という人の役割がきっと大きいのだろう」…と感じつつ、クレジットを眺めていました。あらゆる物事には必ず、表面的に目立ったものの奥にもっと大切な何かが隠されている…いつしかそんな感覚を持つようになっていました。
また、ひとえに“裏方”といっても、音楽というのは作詞・作曲のほか、振り付けや映像制作など、さまざまな作り手が関わって生まれるものです。そのなかで僕は、「曲を書く」という立場を職業に選びました。その選択の基準には、著作に対するロイヤリティーの有無も大きく影響していたと思います。というのも、ダンスの振り付けやMVの監督には、印税が支払われる仕組みがありません。一方で作曲家には、それが明確に保証されていました。自分が過去に書いた曲を、誰かがカバーするたびに、カラオケで歌うたびに、ラジオやテレビなどで放送されるたびに…、経済的なリターンを得られる仕組みが厳然と存在する…。この一点こそが、当時まだ何も持たなかった僕に夢を与えてくれたのです。ちなみに僕には、著作権にまつわる原体験がありました。母方の祖父が、印税収入を稼ぐ人だったのです。祖父は古代中国の歴史書『漢書(かんじょ)』『史記』『司馬遷』を、世界で初めて現代文に訳した人でした。既に他界していますが、祖父の仕事の対価は現在もなお、文庫化や電子書籍化など、新たな節目を迎えるたびに、「印税」という形で家族に引き継がれています。出版されてから既に数十年経ち、少額かもしれませんが、自分の亡き後まで子どもや孫に支払われているのだから、おじいちゃんとしては最高の生き方ではないでしょうか。先に述べた裏方思考の強さと、ロイヤリティーに対する憧れ。この2点が根底にあったからこそ、MVの監督やCD/レコードのジャケットデザインの仕事に興味を持ちながらも、最終的に職業として選ばなかったのだと思います。
独立に向け、音楽業界で修業を積む。
チャンスとは、思いがけないところからやってくるものです。時は90年代、クラブシーンを中心にアシッドジャズのムーブメントがあり、今日的なクラブDJのパイオニア的な存在として、『U.F.O』という3人組のユニットが活動していました。彼らの音楽的な感覚は世界基準で、そのレベルの高さには思わず息をのんだものです。しかし、なんと彼らのプロデュースするアルバムに、僕の作品が収録されることになりました。きっかけは、僕が作ったデモ曲を、彼らのイベントに行って手渡したこと。それを、メンバーの松浦俊夫さんが目にとめて連絡をくださったのです。自分の作品が然るべき人に認められ、仕事として回り始めたことは、たいへん嬉しいことでした。しかし同時に、自分の無知を痛いほど自覚する機会にもなりました。初めて著作権契約書を目にした僕は、その内容がさっぱり理解できなかったのです。こんな状態では、駆け出しの若造だとナメられ、いずれ大人たちに騙されかねない…。危機感を募らせた僕は、まずは一度、音楽業界に飛び込んでみようと考えました。近い将来作曲家として独立するために、権利関係をはじめとした法務的な知識を身につけたいと思ったのです。ちょうどそのとき、東芝EMI(当時)の求人を見つけ、僕はレコード会社で働くチャンスを手にしました。いま振り返っても、なんと良いチョイスをしたのだろうと、当時の自分を褒めてあげたい気持ちになります。レコード会社という音楽業界のド真ん中に飛び込んだことで、新人アーティストの発掘やマネジメントなど、現場のリアルを知ることができ、何より自分の現在地を正確に把握することができました。独立に向け、チェックシートに印を付けるかのように、自分に足りない項目を一つひとつ潰していったのです。会社員として働いた約2年半の間に、20歳そこそこで曲を書きつつ、自ら権利交渉までできるようになっていました。
世間で流行するヒット曲の陰で、孤独な闘いは続いた。
独立してから、自分の作った曲やトラックを、いろんなところへプレゼンに行きました。しかし、僕がやりたい音楽を理解してくれる人は、当初は誰ひとりいなかったのです。そもそも世間で流行っている音楽と、僕がやりたかったそれは、あまりにかけ離れていました。そのうえ、僕は無名の若造ときています。「これが本物のR&Bなのだ!」…と、いくら力説したところで、聞く耳を持ってくれる人はいませんでした。20~25歳の頃は、そのような逆境ゆえのモチベーションが、常に自分のなかに渦巻いていましたね。ときには、クライアントのリクエストと自分のやりたい音楽との乖離に耐えかね、クレジットやギャラを辞退することもありました。若かった僕は、自分の理想とする「まだ世の中にない音楽」を作るべく、必死にもがいていたのです。苛立ちを募らせながら、このような孤軍奮闘の時期はしばらく続きました。最終的に、自分の志す音楽に理解を示してくれるアーティストやスタッフが現れ、何十万人もの人々が聞いてくれるようなヒットにつながったことで、僕の孤独な闘いは、ようやく終わりを迎えたのです。
僕自身が味わった孤独や葛藤は、時代的にも避けられないものであったし、自分にとっても必要な経験だったと思っています。とはいえ、もしも当時の自分が、その後も一人で走り続ける道を選択していたら、今とはまったく異なる音楽家人生になっていたはずです。幸運にも、僕は仲間と共に仕事をする(=共創する)ことの面白さに巡り合うことができました。きっかけは、今から18年ほど前。自分にとって初のスタジオが、青山に完成したばかりの頃でした。その当時、僕のもとには頻繁に若手クリエイターからデモ音源が寄せられたり、彼らの楽曲に対してアドバイスを求められたりする機会がありました。なかにはセンスを感じさせる若手もいて、その熱心さや吸収力の高さには、実に驚かされたものです。僕はいつしか、彼らとのコミュニケーションを心から楽しむようになり、若手クリエイターの育成やマネジメントを、自分の会社でしてみたいと思うようになっていました。僕が最初に契約したクリエイター第一号はUTA(ユウタ)くん。今ではAIや三浦大知、BTSなどのトップアーティストと仕事をする売れっ子プロデューサーへと目覚ましい成長を遂げました。僕にとって、自分を優に超えるような才能が新たに生まれることほど痛快なことはありません。もしも自分が個人経営の音楽家であれば、新たな才能は自分の立場を脅かす存在になりますから、決して心穏やかではいられないでしょう。その点、僕は自分よりも優秀なクリエイターを喜んで仲間に迎えることで、最高のクリエイティブチームとして仕事が受けられるわけです。結果的に、僕ひとりではリーチできなかった人や音楽とのご縁が次々に生まれ、業界やクライアントに提供できる価値の幅も大きく拡がっていきました。個性や強み、キャラクターがそれぞれ異なるプロの集団だからこそ、生み出せる音楽にも多様性が生まれるのです。僕が音楽の仕事をずっとフレッシュな気持ちで続けてこられたのは、圧倒的に優秀かつ素晴らしい仲間がいてくれたおかげです。一人でも多くの若者が余計な苦労をせずに済むような開かれた場所をつくりたいと願ってきました。それが、日本のポップミュージック・シーンの発展につながると信じているからです。
音楽家の無力さを痛感した、東日本大震災。
「ここに仕事を頼んだら間違いない」…僕らは今後も、そのような信頼をいただける音楽のクリエイティブチームでありたいと思っています。自分たちが手がける一曲が、一人のアーティストの音楽人生を、そして多くのリスナーの方々の人生までも変えてしまう可能性があるのだから、責任も大きいのです。
さて、なぜ音楽家である僕が、これまでのキャリアとはまったく畑の違う、飲食ギフトサービスの事業に乗り出したのか…?いろいろな経緯はありますが、直接的なトリガーとなったのは、2011年3月11日に起こった、東日本大震災でした。どんなに素敵な音楽を作ったところで、音楽はそれ自体で空腹を満たしたり、風雨や寒さをしのいだりすることはできません。“生きることそのもの”が脅かされている状況では、エンターテイメントは圧倒的に無力である…この事実を思い知らされたのが、あの震災でした。
もちろん、音楽にも人を救う力があることに、疑いの余地はないと思っています。音楽家として、音という影も形もないものに魂を吹き込み、幸いなことに数億人という人間がそれを聴いて涙したり感極まったりするシーンを、何度となく目にしてきました。また、僕自身、チャリティープロジェクト『VOICE OF LOVE』(2003年)をはじめ、音楽を通じたさまざまな社会貢献活動を続けながら、自分にできることを模索してきました。たとえば、楽曲の売上を、発展途上国の学校建設や楽器寄贈のために寄付してきたことも、その一つです。その際にも、単にお金を渡すのではなく、現地に本当の意味で息づく教育のサイクルをつくる過程にまでこだわり、寄付先も慎重に選びました。ビジョンを共有し信頼できるパートナーを求めて、複数のNPOやNGOを巡ったものです。
しかし、震災以降は、人が生きるためのエッセンシャルな部分をダイレクトに支援できる仕組みを作りたいと、強く思うようになりました。それこそ、“衣食住”にまつわる領域です。だからこそ、『ごちめし』のアイデアを思いついたときには、もはや止められないほどの興奮を覚えたのです。おかげさまで僕自身は、ビジョンを共にできる仲間に恵まれ、幸せな職業人生を歩んでくることができました。これを何かの形で社会に還元したいと模索し続けてきたなかで、ついに辿り着けた感覚があったのです。
『ごちめし』の特徴は、たとえ自分がその場にいなくても、大切な人に食事をプレゼントしたり、友人のレストランの周年などにお酒を贈ったりできることです。また、そのような個人的な使い方の他にも、たとえば商店街単位で店舗にアプリ登録してもらい、ユーザーが街の子どもたちに「ごち」を送り、こども食堂のような社会貢献的な使い方まで、さまざまなシチュエーションに応じて役立てるサービスを目指しています。このような形にこだわった理由は、「ごち」する人のリアクションが生み出す“喜びの総数”が、最大限に増える仕組みを目指したからです。「ごち」した人が現場に介在しない…これは、非常に“音楽的”な感覚に似ています。たとえば、僕が作った曲が自分の手元を離れ、アーティストが表現した時点で、僕の存在はもはや重要ではなくなっています。大切なのは、アーティストとリスナー、それからリスナー同士の結びつきや関係性であって、その曲を作ったのは誰か…なんてことは、音楽から受ける感動の前では些末なことです。そして僕は、それで良いと思っています。一方で、僕がレストランを経営し、多くの人に美味しい食事を提供するという方法もあるでしょう。そこには確かに、一定の喜びは存在し得ると思います。でもそれは、僕としては何かが違うのです。それはもう、僕が音楽家であり作曲家であり、音楽プロデューサーだからというしか、説明がつきません。限られた空間にいる限られた人だけに向けて、ではなく、より多くの人に喜びが波及していくようなサービスを目指したい。そして、「ごち」という一つのアクションから生まれる喜びを、関わる人がそれぞれ自分のものにしてもらいたい…。『ごちめし』というアプリサービスは、まさに僕が理想とする、“食におけるコミュニケーションツール”なのです。
「Pay it forward」の価値観を、社会に浸透させていくサービスへ。
 弊社では、『Your Happiness is My Happiness.』という言葉を社是として掲げています。これは、僕が長らく携わってきた「音楽」の世界にも通じる哲学です。職業作曲家というのは、誰か一人でも作品に喜びを感じてくれる人がいない限り、印税は1円も発生しません。「また聴きたい」「歌いたい」「結婚式の曲として使いたい」…など、誰かの幸せへの貢献の一つひとつが使用料として積み重なり、僕らは生かされているのです。だから、たとえどんなに薄利であったとしても、喜びの総量さえ多ければ、事業として成立するのではないか…。このような仮説をもとに、『ごちめし』はスタートしました。
弊社では、『Your Happiness is My Happiness.』という言葉を社是として掲げています。これは、僕が長らく携わってきた「音楽」の世界にも通じる哲学です。職業作曲家というのは、誰か一人でも作品に喜びを感じてくれる人がいない限り、印税は1円も発生しません。「また聴きたい」「歌いたい」「結婚式の曲として使いたい」…など、誰かの幸せへの貢献の一つひとつが使用料として積み重なり、僕らは生かされているのです。だから、たとえどんなに薄利であったとしても、喜びの総量さえ多ければ、事業として成立するのではないか…。このような仮説をもとに、『ごちめし』はスタートしました。
だから弊社のサービスは最初から、企業や団体と手を組み、いつでも新たなスキームを展開しやすいように設計されています。たとえば、コロナ禍における地方自治体・商工会の緊急支援策として展開している『ご当地ごちめし』、飲食店以外の業界・娯楽施設などを巻き込んだ『さきめし開放』など、これまでにも多くの事例が生まれてきました。僕らは日本全国の街や店舗に、より大きな“活気”と“気持ち”が、「食」を通して連鎖することに期待してきたのです。2019年6月には、商店街や地域の飲食店を巻き込み、「こども食堂」のテストマーケティングもスタート。また2020年には、茨城県境町で、ふるさと納税と町の財源を活用した「こども食堂」の運用が、いち早く始まっています。さらに、『ばんどう太郎グループ』や『コロワイドグループ』をはじめ、飲食店グループとのタイアップによる子ども食堂の展開も本格的に進んできました。そして、2021年2月「まちの飲食店がどこでも社食になる」をコンセプトに、ごちめし加盟飲食店で福利厚生としての社食を提供できるサービス『びずめし』も開始。これは、飲食店の売上向上への貢献はもちろん、地域創生の循環的かつ継続的な支援策になると考えています。企業としても、リモートワークやワーケーション、出張時など、多様な働き方に対応できる社食のスタイルは、社員さんの満足度向上に役立てられるはずです。このように、サービスを介して生まれる喜びの総量が多ければ事業として成り立つという僕らの仮説は、着々と証明されつつあります。そもそも自分さえ儲かれば良いというビジネスは、絶対に長続きしません。奪い合うのではなく共に創り、利益を少しずつ分け合いながら、“面”として広く経済活動を続けていくことが、今の時代に必要な概念だと思うのです。コロナ禍により、この流れはより顕著になったのではないでしょうか。誰か一人の喜びより、店舗、お客様(老若男女)、企業、地域全体…と、喜びの総量が大きいほうが、サービスが拡がるスピードも速いはずです。僕らは人とお店、地域にやさしいビジネスモデルを実現し、「Pay it forward」(ペイフォワード:恩送り・利他)の気持ちが社会に拡がり循環するような、サステナブルで新しい価値観を創造していきたい。むしろ声高に叫ばなくとも、そのような価値観を最も体現したサービスに、自然となっていけたら最高ですね。
また、海外展開も視野に入れています。すでに複数のグローバル企業から事業提携のオファーをいただく機会が増えており、『ごちめし』の中国語版や英語版のリリースを待ち望む声も聞こえています。海外には、日本よりも寄付文化が根付いている国も多いので、サービスへの共感をいただきやすく、確かな手応えを感じています。今後の目標としては、2024年2月末までに、年商30億円規模のサービスへと成長させていきたいと考えています。そして、「Gochi(ごち)」という言葉を、「Mottainai(もったいない)」や「Omotenashi(おもてなし)」に次ぐ、日本から世界に羽ばたく新しい価値観として、たくさんの人々に伝えていきたいと思っています。
◆ 編集後記 ◆
今回の取材を機に、2019年に出版された今井了介さんの著書を拝読した。本のタイトルは、『さよなら、ヒット曲』。なんとも意味深なタイトルであるが、そこには約30年の音楽家人生を歩んできた今井さんならではの、熱くも静かな想いが込められていた。それは、彼がまだ若かりし頃、当時のヒット曲に対して抱いた生々しい感情だ。この大嫌いなヒット曲の数々を、いつか必ず自分の曲で塗り替え、時代を切り拓いてやるんだという野心。そして今度は、自分がつくった楽曲に対して、同じように嫌悪感や対抗心を燃やす若者がいて当然だという想いである。いつの時代にも、追う者と追われる者がいて、その熾烈な競争のなかから、私たちの人生を彩り、記憶に残る素晴らしい音楽が生み出されているという。実のところ、私は音楽を聴くとき、作り手の名前に注目する機会はほとんどなかった。しかし今回、自分が意識せずに聴いてきた曲のなかに、今井さんの作品が多数あったことを初めて知った。個人的には、安室ちゃんの転機となった『Suite Chic』はもちろん、『w-inds.』のイメージが大きく変わった楽曲を、今井さんが手がけていたとは非常に感慨深いものがあった。
さて、そんな今井さんが『ごちめし』のアプリサービス化に向け動き出したのは、あの大ヒット曲『Hero(安室奈美恵)』を書いた直後のこと。音楽家として申し分のない実績を築き上げた彼がなぜ、わざわざ畑違いのフードテック事業などを始めるのか…?『ごちめし』の事業計画書を持参した彼を、金融機関や投資家は不思議に思った。しかも、飲食店から手数料を一切とらないという、前例のないサービスモデルである。結論、『ごちめし』の事業構想は当初、行く先々でまったく理解されず、創業時融資は一円も得られなかったそうだ。確かに表面的に見れば、彼のキャリアと『ごちめし』の事業は、まったく脈絡がないかのように思える。そして、人の善意を拠りどころとする『ごちめし』のコンセプトは、既存のサービスには見られないものだ。しかし、このたび著書を読んで、はっきりとわかったことがある。約20年前、彼が生み出した一つの楽曲が契機となって、日本のR&Bの常識が変わったように、まだ誰にも見えていない未来が、今井さんには見えているのだ。そう、またしても「誰もやらなかったこと」を手がけているのだ。彼にとっては、歌詞やアレンジに込められた想いや意図を制作者としてアーティストやスタッフに根気強くプレゼンしてきた経験と、今回も同様なのだろう。今、『ごちめし』のコアバリューやビジョンについて、ファウンダーである彼自身が地道な発信を続けているのだから。彼はいつだって、我々の先を走り過ぎている。だから、きっと時間差はあるだろうが、『ごちめし』を通じて今井さんが浸透させたいと願っている「Pay it forward(恩送り)」の価値観は、時を経て必ず、世の中に浸透していくことだろう。そんなやさしい未来が訪れる日が、今から楽しみである。
取材:四分一 武 / 文:アラミホ
メールマガジン配信日: 2021年12月1日