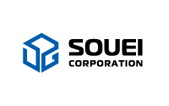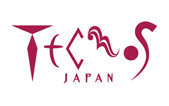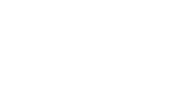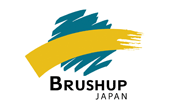アメリカ足病医学に基づく正しい靴選びと、特許インソール(オーダーメイドソール)によるフットケアサービスを提供する足の専門店『 足道楽(あしどうらく)』。東京・神奈川・埼玉に直営22店舗を展開する同ブランドは、40~60代の男女を対象とした第三者機関による「矯正型インソールに関する調査(2020年)」において、「身体の痛みを改善する」「身体の歪みを改善する」「疲労が軽減されたと感じる」の全3項目で、満足度No.1を獲得している。身体の痛みや不調からの解放は、誰もが望む願いであり、人生の幸福度に大きく影響する。数ある健康法や施術のなかで、体験者に確かな満足度を提供している『足道楽』。創業者の馬場氏が「足」の健康に着目した背景には、どのようなストーリーがあるのだろうか。本稿では、『足道楽』ならではの独自性をお伝えすると共に、ビジネスの起源となった創業者の原体験に迫りたいと思う。
私たちは、アメリカ足病医学に基づく正しい靴選びと、特許インソール(オーダーメイドソールによるフットケアサービスを提供する足の専門店『 足道楽(あしどうらく)』を、東京・神奈川・埼玉に22店舗展開しています。2008年、町田に1号店をオープンするまで、スキー・スノーボードをメインに扱うスポーツショップを運営してきました。当時から我々は、米国医療認定インソール『 superfeet(スーパーフィート)』の技術を用いて、スキーヤー、スノーボーダーの方々の「足」に着目し、その矯正に注力してきました。直立二足歩行をする人間にとって、足は全身を支える土台の役割を担う重要なパーツです。まずはその形状を本来あるべき状態に整えることで、骨格全体の歪みまで矯正し、痛みの改善やパフォーマンスの向上に貢献できるのです。スキーヤー、スノーボーダーに限らず、スポーツをする人、またはしない人も、その多くが膝や腰の痛みをはじめとした身体の不調に悩みを抱えています。しかも、その症状は加齢と共に悪化していくケースがほとんどです。多くの人々が抱える症状の根本原因は、主に2つ。1つは、スポーツや職業、日頃の姿勢をはじめとした、各々の生活習慣の蓄積が引き起こす足の骨格の変形によるもの。もう1つは、自分の足に合った靴を履いていないことです。この2点に同時にアプローチするソリューションが、これから高齢化社会が本格化する日本に必ず貢献できると確信し、『足道楽』は生まれました。おかげさまで、足病患者の方々はもちろん、有名プロアスリートの方々からも厚い信頼をいただいております。
幼少期を支配し続けた、極度の「不安症」。
生まれは滋賀県守山市です。実は私、幼少期から小学1年生くらいまで、ほとんど記憶がありません。ただ一つ、今も鮮明に覚えているのは、毎朝めざめるたびに襲ってくる、「恐怖」と「不安」の感情だけ。原因は今もわかりません。人がコワイ…。とにかく世界が恐ろしい!そんな極度の不安症を抱えた当時の私にとって、保育園の迎えが来てしまう「朝」というのは、夢に見るほど恐ろしい時間でした。他の兄弟は、難なく送迎バスに乗り込んでいきます。一方で、逃げ回っては母のミシンにしがみつき、「イヤだイヤだ」と泣きわめく私…。それを無理やり引きずり出され、バスに押し込まれるという大騒動を、毎朝のように繰り返していたのです(笑)。
そんな私の苦悩の日々は、小学校に上がっても続きます。特に給食の時間というのは、私にとって悪夢そのものでした。たとえば、学年の異なる生徒たちと向かい合って給食をとるという、恐怖のシチュエーションに置かれた日のこと。見知らぬ相手を前にした私は、あまりのストレスからパニックに陥り、モノの食べ方さえ忘れるという顛末。これに見かねた両親がまた、休日になると私を外食へ連れ出すのです。目的は、外の世界に慣れさせること。しかし、外出先ではそれ以上に、壮絶な試練が待っていました。慣れない空間や極度のプレッシャーから、私は食べ物が飲み込めず、毎回のように嘔吐していたのです。そこまで苦しい思いをするというのに、訓練だからと何度も連れていかれる…。両親も、きっと必死だったのでしょう。当時はもう、生きることがしんど過ぎて、子どもながらに「早くラクになりたい…」と切望していましたね(笑)。
唯一の特技は、足が速いこと。
子どもって、相手の怯えや心の弱さを敏感に察知するもので、私はよく彼らの〝からかい〟の対象になりました。しかし、そんな私にも唯一、特技と言えるものがありました。それは、足の速さです。年少の段階で年長の子どもよりも速く走れた私は、その一点だけで周囲から褒められ、チヤホヤしてもらえることを知りました。それ以外は、何ひとつとして自信を持てないままでしたが、心のなかに確かな誇りを見つけることができたのです。
小学1年生になった私に、突然の転機が訪れます。いつものように、私をおちょくってきたクラスメートを、つい衝動的にしばいてしまったのです(笑)。思わぬ一撃を喰らって泣きわめく相手を見たとき、「なんだか自分、やっていけるかも…」と、初めて自信に近い感覚が芽生えました。この日を境に、私の創意工夫人生が始まります。目の前の不安や恐怖が、決して消えたわけではありません。依然として、朝を迎えるのは怖いまま。しかし、そこから逃げることが許されないなら、どうしたら乗り越えられるかという発想に変わったのです。たとえば、大嫌いな給食の時間をやり過ごすための工夫。まず、朝食を抜いて登校します。空腹の状態で昼を迎えれば、さすがに少しは食べるのがラクになると考えたからです。当時はまだ、完食するまで席を立つことが許されないなんて、当たり前の時代でした。牛乳嫌いの私には大ピンチです。そこで私は、コーヒー牛乳用の粉末を譲ってくれるクラスメートを、あらかじめ把握するようになりました。かき集めたコーヒー粉末で牛乳の味をごまかし、息を止めて胃に流し込めば良いのです。先生やクラスメートの目を盗んでは、完食を装ってこっそり廃棄…(笑)。毎日が真剣勝負ですから、鋭い観察力が鍛えられました。こうして生きるコツを掴み始めた小学2年生の頃には、不安や恐怖に支配されることがだいぶ減りましたね。
自慢の短距離走に、ライバル出現のピンチ!
小学校の高学年になった頃には、持ち前の運動神経に助けられ、いわゆる〝負け知らず〟の時代を過ごしていました。野球ではリトルリーグに所属したり、サッカーではJリーグの候補選手たちと共に練習をしたり。走ることも負けなしでした。
しかし、中学校に進んだとき、初めて「負け」を経験します。個人表彰が欲しかった私は、野球やサッカーなどの団体競技ではなく、陸上部を選びました。ところが…。100m走のタイムで、どうしても勝てない相手が部内にいたのです!これは青天の霹靂でした。自分の負けを認めたくなくて、必死で練習に没頭しましたが、それでも適わぬ相手だったのです。しかしそのライバルが、大会を前に盲腸で入院。結果は秋の大会で私が勝利し、そのまま県大会も優勝!当時の100m走のタイムは11.2秒。ジュニアオリンピックの強化チーム入りも果たしました。おかげさまで、多くの強豪校から入学のオファーをいただく結果になりました。
忘れていた頃に、「不安症」が再発…。
私は第一志望校への進学を早々に決め、大学までストレートで進学できる権利も手に入れました。しかし…。入学願書を出す時期になって、ずっと影をひそめていた私の「不安症」が、急に再発したのです。高校へ行ったら、自分は絶対に落ちこぼれてしまう…!事実、進学予定だった高校の偏差値は、実力よりもだいぶ格上。なにせ私の中学の成績は、ビリから数えたほうが早かったのです(笑)こんなヒドい成績で、もしも頼りの陸上までダメになったら、いったい俺はどうしていくねん…!頭のなかに生まれた不安は、どんどん膨れ上がっていきます。結果的に、私は推薦をいただいた高校のなかで、自分の学力レベルにあった学校に進むことにしました。もちろん、周囲には理解されず、多くの反対も受けました。しかし、陸上で勝ち続けていくことの厳しさも身にしみていた私は、「もしも」の不安に打ち勝つことができませんでした。とにかく少しでも、心に余裕が欲しかったのです。
高校時代も県大会で優勝するなど、陸上競技で一定の結果を残すことができました。一方で、ケガや故障に悩まされる機会も増えていきました。たとえば、一度の捻挫がクセになり、負傷した部分を庇って走っていると、他の部分に新たな支障が出てきます。ケガをすれば、思うように結果が出なくなる。結果が出ないと、メンタルが落ち込んでいく…。自分の意志に反して、将来的に競技を続けられないリスクを感じた私は、陸上での推薦はやめて、大学受験をすることにしました。
大学へ進学した後も、しばらく競技を続けていました。しかし、1年生の終わり頃、繰り返す膝の不調と付き合いながらの競技生活に限界を感じ、辞めることを決意したのです。一度は陸上で食べていくことも考えた身です。競技人生を諦めることには、やはり無念の想いが強かったですね。
物心ついてからずっと、ほぼ陸上オンリーの人生でした。煙草も吸わなければ、お酒も飲みません。いわゆる〝遊び方〟をまったく知らないのです。そんな私に、新たな世界を見せてくれた友人がいました。彼に誘われ、初めて京都のディスコを訪れた日の感動を、今でも鮮明に覚えています。こんなに楽しい場所が世界にあったのかと、シビれるほどの衝撃を受けたのです(笑)自分が踊る振り(いわゆるユーロビート)に合わせて、ダンスホールが一体となる快感ときたら…!ディスコの楽しさに目覚めてしまった私は、それから毎晩のように入り浸っていましたね。別にモテたかったわけではありません。陸上選手としてのアイデンティティを失った私にとっては、新たな〝居場所〟を見つけられたことへの喜びの境地だったのです。当時はバブル真っ盛り。週末にはホールを貸し切って、企業の協賛を集めたり、芸能人を呼んだりして、ダンパ(ダンスパーティー)の企画に熱中していました。非常に楽しい日々でしたね。
大学卒業後、繊維商社で経験を積む。
就職活動の時期を迎える頃の私は、ある程度の自己分析ができていました。経験則から感じていたのは、いわゆる花形企業の〝4番バッター〟的なキャリアは、自分にはムリだということ。就職先に置き換えると、銀行や証券会社に就職し、ガンガン出世していくようなイメージです。それなら自分は、別の勝ち筋を探そう。王道ではなくても、ニッチで小さな会社の〝4番バッター〟で活躍しよう!と考えたわけです(笑)
最初に就職したのは、京都の繊維商社でした。アパレルには昔から関心があったからです。入社後まもなく、商品の企画から販売、経理に関することまで、大きな裁量を任されるようになりました。ハードワークはしんどかったけれど、若いうちから申し分なく成長できる環境を与えていただいたことに、今でも感謝しています。
転職先のスポーツショップで、プライドがズタズタに…。
25歳の終わり頃、その当時、地元の滋賀県守山市で、大学時代の先輩がスキーショップの店長をしていました。20坪ほどの小さな店舗でしたが、売上は好調とのこと。先輩から直々に仕事の誘いを受けた私は、「地元だし、今より給料も良くなるのなら…」と、転職することにしたのです。しかし、いざ入社してみると、私の同僚となるのは、アルバイトスタッフばかり。自分は大卒で、陸上でもそれなりの結果を残してきたのに…。置かれた境遇に誇りを待てないでいた私は、知り合いが来店したときに、思わず隠れるような心構えで働いていたのです。しかし、そんな私の小さなプライドなど、現場は知ったことではありません。アルバイトの子たちが、めちゃめちゃ売っているわけです。さらに…。「馬場さん、これ取ってきて~!」と、年上の私に指図までしてきます。店舗の構造上、1階が売り場となっており、商品は上の階まで取りに行く必要がありました。私には、スキーの経験も、知識もないのは確かです。しかし、いくら新人だからといって、こんな扱いを受けるなんて想定外でした。なぜなら私は、店長から引き抜かれて入社してきた人間。年下のアルバイトにコキ使われるなんて、まったく聞いていませんでした。まぁ、初日だし仕方ないか…。堪忍した私は、彼らが商品を売るたびに7階、8階へと駆け上がりました。その数なんと、70往復ほどでしょうか(笑)翌日から、店長に必死にアイコンタクトを求める私。華麗にスルーを決め込む店長。そんな納得のいかない状態が2ヵ月ほど続いた頃、私はついに音を上げました。妻に辞めることを打ち明けたのです。
妻の言葉で一念発起!心を入れ替え、幹部へと駆け上がる。
当時はちょうど、子どもが生まれたタイミング。そんな私に、妻はピシャリと言い放ちました。「あんた、子ども居てんのに、もう辞めるの?なんでそういうことになるかわかる?根本的に、あんたが結果を出してないからや。引き抜かれたはずの人間だとか、スキーの経験がないとか、そんなのぜ~んぶ言い訳!引き抜かれたって主張するなら、それだけの結果を出してから言え!」…と。悔しいけれど、ぐうの音も出ないほどの正論でした(笑)。
妻の言葉で目を覚ました私は、分厚い商品カタログを2日間ほどで丸暗記。営業時間に階段を昇り降りする合間にも、商品知識を身につけるための勉強に没頭しました。商品の販売にも力が入ります。積極的に話しかけるようになったのです。相手を楽しませる接客が評判を呼び、私にもファンができるようになりました。仕事は圧倒的に楽しくなり、結果も自然についてきます。すると…。私の変化に気づいたのか、もしくは店長が伝えてくれたのか、いつしかアルバイトのメンバーが、自ら上の階まで商品を取りに行くようになったのです。すべては自分次第だったことを、改めて実感した瞬間でした。
そこからは、自分の存在価値をもっとアピールしていこうと、積極的に仕事の幅を拡げていきました。たとえば、倉庫の在庫管理を受け持つようになったり、店舗のディスプレイを手がけるようになったり。既存のメンバーにはない、私ならではの価値を出そうと努めたのです。その頃には、みんな私に敬語を使うようになっていましたね(笑)さらには、商品のバイイングを任せてもらったり、納品伝票の管理を仕組み化したり、広告づくりを手がけたり…。小売にまつわる業務は、すべて経験させてもらいました。手を挙げたからには責任が伴うので、それはもう必死にやりました。時を経て、入社当時は年商数億円程度だった会社が数十億円へ、店舗も1000坪へと規模を拡大していました。そこへまた、スノーボードブームが到来します。英語も話せない私が、海外へ商品のバイイングに行かせてもらうなど、大きな会社にいたら経験できないことを、すべて任せてもらえました。「俺がせんとあかんねん!」と、使命感に燃えていましたね。しかし…。入社して10年、私が35歳になった頃、私を誘ってくれた店長が会社を退職することになります。それと同時に、会社の方針も徐々に変わっていきました。それなりのポジションや給料をいただいていた私としては、会社に残るという選択肢もありました。とはいえ、ここで安定を選ぶより、新たなチャレンジがしたいという気持ちもあったのです。今から転職するとしても、「雇われ」の身で今以上に裁量が得られる会社はないこともわかっていました。もう、自分でやるしかない。もともと起業を目指していたわけではありませんが、結果的に独立する流れになったのです。
そもそも起業する予定などなかった私は、数年前に地元に家を建てていました。それなのに、懇意にしていた仕入れ先から、近場で開業するなら商品は卸せないと言われてしまったのです。これは商習慣なので仕方がありません。それなら、東京へ行くしかないか…。私のなかで大阪の選択肢はなかったので、人口の多い商圏となると、必然的に東京でした。しかし、縁もゆかりもない東京で、いったいどこに出店すれば良いのだろう…?当時から、スキー・スノーボードのメッカといえば「御茶ノ水」。とはいえ、新参者の我々がそのような激戦区に踏み込めば、すぐに潰されるに決まっています。資金も実績もない私たちには、価格競争に巻き込まれず、独自の価値で勝負できるような商圏が必要でした。それなら「東京23区外」だ!そこで候補地にあがったのが「町田」です。今となっては笑い話ですが、「町田がアツい!」と聞きつけて、夜行バスで視察に駆けつけた我々は、土地勘がないために「町田」ではなく「田町」を訪れていました(笑)。後日、気を取り直して「町田」の駅に降り立ったとき、町の雰囲気や人通りに触れ、「ここで起業しよう!」と直感的に決めました。すぐさま物件探しを開始すると、とある不動産屋の社長に出逢いました。彼は偶然、私と同い年。独立起業して成功した人で、同じように挑戦を始める私たちを、心から応援してくれました。彼の紹介で初めて契約した60坪の物件が、我々の記念すべき第1号店『ビーズイースト』です。
さてさて、ついにスタートです。スタッフは、オール関西人!挨拶はもちろん、「おおきに!」。みんなで元気に営業しようと、最初はテンション高く意気込んでいました。しかし、オープンの日が近づくにつれ、持病の不安症が私を襲います。東京なんて知らない土地で、本当に成功できるのだろうか…。途端に疑念が顔を出すのです。そして、忘れもしない夜のこと。近所の居酒屋で私たちが飲んでいると、近くにいた男性客が、急に席を立ちました。その男は、店主に衝撃的な一言を告げたのです。「今日は帰るわ。俺、関西人キライなんだよね」…と。そもそも心が弱っていた私に、これはトドメの一撃でした。
怯え切った私は、「関西弁の接客は辞めておこう」と、翌日から急に方針を変えました。そうは言っても東京弁なんて、みんな喋れないのです(笑)。そして、オープンを直前にひかえたある日のこと。今度は近所のおばちゃんの言葉に救われたのです。「関西人だからって、こっちの人は嫌っているわけじゃないのよ。明石家さんまも紳助も嫌われてないでしょ。真心はいつか通じる。心配せずに素のままで行きなさい」…と。次の瞬間、「やっぱり関西弁で行くぞ!」と、仲間に号令をかけている自分がいました(笑)。
お客様への真摯な関わりこそ、自分たちの価値。
2001年10月6日。前月の世界同時多発テロの影響で、海外から商品が入って来ないというトラブルに見舞われつつ、なんとか無事にオープンの日を迎えました。開店から数日間は少々の売上が立ったものの、そこからまったく売れない日々が続きました。創業メンバーは全員、地元に家族を残して東京へ来ています。狭いアパートでの共同生活、毎日が松屋、ココイチ、幸楽苑、のローテーション。店舗へ向かう車内では、会話ひとつありません(笑)それでも営業が始まれば、来てくれたお客様に渾身の笑顔で接客しました。自分たちがなぜ東京へ来て、どんな想いでやっているのか、とにかく伝え続けるしかなかったのです。
潮目が変わったのは12月のこと。ボーナスの時期に入った途端、それまで一日数千円だった売上が、一気に数十万円へと化けたのです。このとき初めて、一人ひとりのお客様に心を込めて接していた我々の価値が、確実に相手に伝わっていたことを実感したのです。そこからたった4ヵ月間で、売上1億円を達成。目が回るほどの忙しい日々でしたが、お客様に求められることが嬉しくて、深夜0時まで休まず営業したものです。スキー・スノーボード業界は、シーズン中の半年間だけ稼いで、オフシーズンは休むのが通例です。しかし、創業当初の私たちに、半年間も休めるほどの余裕はありません。オフシーズンをどう乗り切るかに頭を悩ませていた私に、偶然の好機が訪れます。以前に知り合っていたサーフボードメーカーの社長から、自社の商品を扱って欲しいとのオファーをいただいたのです。運が良いことに、社内にサーフィン好きが一人いました。さらに幸運だったのは、タイミング良くサーフィンブームが到来したこと。サーフボードが売れに売れ、無事に夏を乗り切ることができたのです。
他のショップにはない、尖った価値を追い求めて。
当時はまだ、インターネットが今ほど発達していない時代です。私たちは、雪山に関わる情報を自ら足を使って集め、海外との直取引から仕入れた最新情報も、正規メーカーより早く入手し、お客様に惜しみなく提供していました。「あの店に行けば、いろんなことを教えてくれる」…次第にそんなクチコミが拡がり、お客様が集まるようになりました。
当時のスノーボードショップの評価といえば、『 BURTON(バートン)』に代表される人気ブランドの限定商品が揃うかどうかに左右されるのが一般的でした。いわゆるメーカー主導型のマーケティングです。〝ブランドありき〟の勝負では、自分たちに勝ち目はない…。売上は順調に伸びてはいましたが、永続させるには大手と異なる戦略が必要でした。そこで考えたのが、「ブーツ」にこだわること。どんなにうまく滑れても、足が痛ければ楽しくないし、続けることはできません。そこで、一人ひとりの足に合った、オーダーメイドのブーツを作ろうと考えたのです。我々が目をつけたのは、〝サーモインナー〟と呼ばれるブーツ成型技術でした。個々の足型にフィットするブーツが作れることはもちろん、たとえ型崩れを起こしても、再び熱を当てることで焼き直しができるのです。そうはいっても当時はまだ、その技術に認知度がありません。そこで私たちは、お客様に〝試し履き〟を勧めることで、先に価値を実感いただく戦略をとりました。結果は狙い通りの大好評!実際に履いてみたことで、価値を感じたお客様が次々と購入。そこからクチコミが拡がっていきました。私たちの探求はさらに続きます。より良い滑りや足の快適性を求めるなら、やはり〝インソール〟にもこだわるべきだという結論に至りました。「足」に関する研究を深めていた私たちが導入したのは、アメリカ足病医学協会認定のカスタムインソール『 superfeet(スーパーフィート)』。日本では認知度のないブランドのうえに、インソールに2万円超のお金をかけること自体、一般的ではありませんでした。しかし、伝え続ければ必ず価値を感じていただけることを経験から知っていた我々は、一人ひとりのお客様に、丁寧にご案内を重ねていきました。その結果、気づいたときには『 superfeet(スーパーフィート)』の年間販売数世界一のショップになっていたのです。起業当初、「都心の人は、わざわざ町田までは絶対に来ない」と言われていました。しかし、本当に良い商品と情熱があれば、お客様は必ず足を運んでくれる。そう確信できる経験となりました。
2006年、トリノオリンピック開催年のことです。来日したフィンランドのスノーボードチームから、日本で最も〝インソール〟に詳しい場所を訪れたいとのリクエストがあったようで、私たちに問合せがありました。そこで、嬉しい事件が起こります。来店してインソールをつくった4人の選手のうち、なんと3人がオリンピックで入賞したのです!これは、願ってもない宣伝効果でした。「あの店に行くと、足に詳しいスタッフがいる」…この頃には、お客様のクチコミから、私たちがスノーボードショップとして、独自のポジションを築きつつあることを実感する機会が増えました。一方で、このメンバーだからこそ提供できる価値であり、多店舗展開が難しいこともわかっていました。店が増えないということは、会社の成長に限界があるということです。この先どのように事業を伸ばしていくべきか、新たな課題が見えた時期でもありました。
そんな折、ずっと元気だった私の祖母が亡くなりました。きっかけは、転んで骨折したこと。当初は私たち家族も、そこまで深刻には捉えていませんでした。しかし、ひとたび骨折した日を境に、祖母は急激に弱ってしまったのです。体重が落ち、喋れなくなったと思ったら、食べられなくなり、二度と歩けなくなり…。1年半ほど苦しんで亡くなった祖母を見て、私は大きなショックを受けました。人間、自分の足で歩けないだけで、人生最後のシーンを、こんなにも悲しいものにしてしまうのかと。一生涯、自分の足で歩けることは、人生の幸福度を確実に高める重要な条件になる。このとき自分のなかに生まれた想いが、『足道楽』の事業アイデアにつながっています。ウィンタースポーツを楽しみたい人だけが対象ではない。日本が高齢化社会を本格的に迎えるにあたり、「足の健康」はますます重要になると確信したのです。
すべての人に、一生歩き続けられる人生を。2008年6月、私たちは新たなビジョンを掲げ、『足道楽』をスタートしました。足や身体の痛みに悩むシニア層までターゲットを拡げ、インソールの販売に乗り出したのです。案の定、最初はまったく売れません。当時はまだ、インソールの市場自体が小さく、足の健康に寄与するという認識も世間になかったので、ターゲットにリーチするためには試行錯誤が必要でした。しかし、この取り組みの価値を誰よりも信じていた我々は、先駆者としてコツコツと啓蒙活動を続けてきたのです。
開業後、約3ヵ月間の一日の売上は、良くて5千円程度でした。つまり、主力商品のインソールは、ほとんど売れていないのです。そこに突如、神風が吹きます。偶然にも、日テレ『ぶらり途中下車の旅』の取材が入り、舞の海関が来店されたのです。オーダーメイドのインソールを体験した舞の海関が放送中に発したのは、ひたすら「痛い」という言葉だけ。一言も、商品の良さは口にしていません(笑)しかし、放送翌日から100件に上る電話が殺到!一日の売上が、約70万円に跳ね上がったのです。売上が伸びたことはもちろんですが、やはり「足」に悩みを抱える人たちがこんなにも多くいたこと、自らの仮説が正しかったことに、私は大きな手応えを感じました。諦めなければ絶対に行ける!トップを任せていた社長の接客が好評を呼び、『足道楽』のファンは着実に増えて行きました。お客様の反応から確信を得た私たちは、多店舗展開をスタート。おかげさまで22店舗まで拡大し、多くの方々に愛されるブランドへと育てていただきました。とはいえ、まだまだ発展途上。高齢化が進む今、足や身体の不調に悩む方々は全国規模で増えており、私たちの価値をお届けできていない潜在的なお客様はたくさんいらっしゃいます。将来的には、過疎地への出張サービスも視野に入れていますし、「足に悩んだら足道楽!」が常識になる未来を描いて、引き続きチャレンジを続けてまいります。
◆ 編集後記 ◆
今回、取材前に『足道楽(あしどうらく)』町田本店に立ち寄ってみた。扉を開けると、「こんにちは~!」と、男性スタッフが元気な声と笑顔で迎えてくれた。「何かお探しでしょうか?」と、すぐに駆け寄ってきてくれる。店内中央のスペースでは、高齢の女性に熱心に接客を行う男性スタッフの姿。どうやらインソールを作成中のようで、女性は宙に浮くほどの高い椅子に座っている。『足道楽』では、国際特許の無加重システムを使用することで、体重のかかっていない本来の正しい足の状態でインソールを作成するそうだ。無加重とは、足が宙に浮いた状態のこと。地面に足がついた状態だと、潰れた足に合わせてインソールを成型することになる。それでは矯正能力を持たないため、身体の歪みが改善されないそうだ。女性が高い椅子に座っていた理由は、本来の足の形状に合わせてインソールを作成することが目的だったのだ。無加重システムの導入により、正しい足の状態に矯正されて立つことになるので、インソールを入れた直後はやはり痛い。しかし、その矯正力により、足病や生活習慣病を解消しやすくなるというわけだ。女性は真剣に男性スタッフの説明に耳を傾け、症状を訴えている。一人ひとりの悩みに寄り添った接客を行うことで、地域から愛されている店舗なのだと感じられた。
さて、取材に応じてくださった馬場会長。軽快な関西弁が印象的だ。話し上手でユーモアに溢れており、あっという間の90分だった。幼い頃に悩まされたという〝気の弱さ〟なんて、もはや見る影もない(笑)しかし、幼少時代は本当に、「こんな恐ろしい日々が、おじいちゃんになる歳まで続くのか」と、絶望感さえ感じたという。逃げられないなら打破しなければならない。そう覚悟を決めたときの馬場少年の創意工夫のエピソードの数々には、なかなかの迫力があった。そこまで極度の不安症を乗り越えられた理由について伺うと、極度の「負けず嫌い」が、生来の〝気の弱さ〟をギリギリのところで上回ったのだと分析されていた。当時はご両親も、相当に悩んだことだろう。実際に、母親のノートには、「私ノイローゼ」と、震えた字で書かれていたそうだ…(笑)そんな気弱だった少年が今、仲間を率いて大きなビジョンの実現に挑戦している。『足道楽』のさらなる発展に、今後も期待したい。
取材:四分一 武 / 文:アラミホ
メールマガジン配信日: 2021/6/29